トゥーランドット
OCT 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
トゥーランドット – ジャコモ・プッチーニ
終幕:ルチアーノ・ベリオ
上演時間:2時間40分(休憩1回を含む)
言語:イタリア語
字幕:ハンガリー語、英語、イタリア語
中国の王女トゥーランドットは、三つの謎を解けた者でなければ結婚しないと誓います。ジャコモ・プッチーニの最後の未完のオペラは、おとぎ話的要素と社会哲学的テーマを同時に扱っています。今回の新制作は、世界的に評価の高い振付家ドーラ・バルタによる演出で、オペラ界でも最も謎めいた女性のタイトルロールに女性として挑みます。彼女の演出は、ムーブメントとフィジカル・シアターによる躍動的な舞台言語、そしてオペラの原作となったカルロ・ゴッツィの戯曲にも影響を与えたコメディア・デラルテの視点から作品にアプローチします。ダンスと動きの抽象的な表現は、作品に込められた哲学的な要素を際立たせ、同時に権力のテーマも浮き彫りになります。なぜならトゥーランドットの父である皇帝は、娘の夫だけでなく、中国の未来の支配者も探しているからです…
年齢制限:14歳未満のお子様にはご鑑賞をおすすめしておりません。
あらすじ
時と場所:いつとも知れない伝説時代の北京
第1幕
宮殿(紫禁城)の城壁前の広場。役人が群衆に宣言する「美しいトゥーランドット姫に求婚する男は、彼女の出題する3つの謎を解かなければならない。解けない場合その男は斬首される」今日も謎解きに失敗したペルシアの王子が、月の出とともに斬首されるべく、喝采する群衆の中を引き立てられてくる。敗戦により、国を追われて放浪中の身であるダッタン国の王子カラフは、召使いのリューに手を引かれながらさ迷う盲目の父、ダッタン国の元国王ティムールを発見し、3人は互いに再会を喜ぶ。ペルシア王子処刑の様子を見にトゥーランドット姫が広場に現れ、カラフは一目見てその美しさの虜となる。ティムール、リュー、そして宮廷の3大臣ピン、ポン、パンが思いとどまるよう説得するが、カラフはトゥーランドットの名を叫びながら銅鑼を3回打ち鳴らし、自らが新たな求婚者となることを宣言する。第1幕では、トゥーランドット姫は一切声を発さない。
第2幕
ピン、ポン、パンの三大臣が軽妙なやりとりで姫とカラフの噂話をしている。そのうち、帝の出御となり群衆が集まる。万歳の叫び声の中、皇帝アルトウームがカラフに無謀な試みをやめるよう説得するがカラフは耳を貸さない。こうして姫が冷やかな表情で出てくる。
カラフの謎解きの場面。トゥーランドット姫は、何故自分がこのような謎を出題し、男性の求婚を断ってきたのかの由来を改めて述べる「かつて美しいロウ・リン姫は、異国の男性に騙され、絶望のうちに死んだ。自分は彼女に成り代わって世の全ての男性に復讐を果たす」。
第一の謎「毎夜生まれては明け方に消えるものは?」カラフ曰く「それは希望」第二の謎「赤く、炎の如く熱いが、火ではないものは?」「それは血潮」カラフは2つまでも正解を返す。最後の謎「氷のように冷たいが、周囲を焼き焦がすものは?」カラフは暫く悩むが、これも「トゥーランドット!」と正答する。
謎がことごとく打破されたトゥーランドット姫は父アルトゥーム皇帝に「私は結婚などしたくない」と哀願するが、皇帝は「約束は約束」と娘に翻意を促す。カラフは姫に対して「それでは私もたった一つの謎を出そう。私の名は誰も知らないはず。明日の夜明けまでに私の名を知れば、私は潔く死のう」と提案する。
第3幕
北京の街にはトゥーランドット姫の命令が下る。「今夜は誰も寝てはならぬ。求婚者の名を解き明かすことができなかったら住民は皆死刑とする」カラフは「姫も冷たい部屋で眠れぬ一夜を過ごしているに違いない。夜明けには私は勝利するだろう」とその希望を高らかに歌う。ピン、ポン、パンの3大臣は多くの美女たちと財宝を彼に提供、姫への求婚を取り下げるよう願うが、カラフは拒絶する。ティムールとリューが、求婚者の名を知る者として捕縛され連行されてくる。名前を白状しろ、とリューは拷問を受けるが、彼女は口を閉ざし、衛兵の剣を奪い取って自刃する。リューの死を悼んで、群衆、3大臣など全員が去り、トゥーランドット姫と王子だけが残される。
王子は姫に熱い接吻をする。リューの献身を目の当たりにしてから姫の冷たい心にも変化が生じており、彼を愛するようになる。ここで王子ははじめて自らの名がカラフであることを告げる。「名前がわかった」と姫は人々を呼び戻す。
トゥーランドットとカラフは皇帝の玉座の前に進み出る。姫は「彼の名は……『愛』です」と宣言する。群衆は愛の勝利を高らかに賛美、皇帝万歳を歌い上げる中、幕。
プログラムとキャスト
指揮:マルティン・ライナ
トゥーランドット – シルヴィア・ラーリク、チラ・ボロシュ
皇帝アルトゥーム – デーネシュ・グヤーシュ
ティムール – アンドラーシュ・パレルディ
カラフ – ボルディジャール・ラースロー、ギオルギ・ストゥルア
リュー – ポリーナ・パシュティルチャーク、ガブリエッラ・レタイ・キシュ
ピン – アザト・マリク
パン – ティボール・サッパノシュ
ポン – ボトンド・パール(オペラ・スタジオ)
官吏(マンダリン) – アンドラーシュ・キシュ
ハンガリー国立歌劇場の管弦楽団、合唱団および児童合唱団による上演
クリエイティブチーム:
ドーラ・バルタ
イルディ・ティハニ
ゾルターン・カトンカ
ドーラ・バルタ
クララ・ラーミ
キンガ・ケステヘイ
エリカ・トート
アッティラ・トロニョキョイ
ユディト・ニクライ
ダーリウシュ・テレミ
パールマ・ヒデグクティ
バラージュ・カルヴィン
カタリン・ドマン
ラースロー・バルタル
ニコレッテ・ハイゼル
ガーボル・チキ
ハンガリー国立歌劇場
ハンガリー国立歌劇場(ハンガリーこくりつかげきじょう、ハンガリー語: Magyar Állami Operaház)は、ハンガリーの首都ブダペストにあるネオルネッサンス建築の歌劇場。
概要
1858年創設。グスタフ・マーラーが音楽監督を務め、黄金時代を築いた。以後、エルネー・ドホナーニやフェレンツ・フリッチャイ、オットー・クレンペラー、ヤーノシュ・フェレンチクらが歴代音楽監督として名を連ね、リヒャルト・シュトラウス、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、ヘルベルト・フォン・カラヤンなどの巨匠達も客演指揮を行っている。
初演された主な作品に、バルトークのバレエ「かかし王子」(1917年)、歌劇「青ひげ公の城」(1918年)や、コダーイの歌劇「ハーリ・ヤーノシュ」(1926年)がある。
歌劇場の専属オーケストラはブダペスト・フィルハーモニー管弦楽団の名称で知られている。
なお、同じくフリッチャイやフェレンチクが音楽監督であったハンガリー国立交響楽団(現ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団)は、この歌劇場のオーケストラとは別団体である。
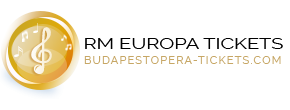
 JP
JP EN
EN DE
DE IT
IT FR
FR ES
ES RU
RU RO
RO
 座席表
座席表 